2歳・3歳で言葉がなかなかでない……
そんな不安に寄り添う、言語聴覚士ママによる家庭で実践できるサポート法を丁寧に解説しますね。

言語聴覚士(ST)×保育士として児発と放デイで働いていますよ。
生まれてきた時は泣くことしか出来ない赤ちゃん。
いつお話してくれるかな?って楽しみですよね。
そんな中、自分の子どもだけがなかなかお話してくれないと不安な気持ちになると思います。
目次
言葉がでない時に考えられること
初めにお伝えしたいことは、必ずしも言葉が出ない=発達に問題があるというわけではないのです。
現在は発達障害のことを神経発達症といったり、ADHDやASDなどといったりしますが、このブログでは分かりやすく「発達の個人差」や「発達がゆっくり」などと表現しますね。
言葉が出ない理由
- 発達の個人差
- 聴力の問題(難聴)
- 口周りの筋力の問題
- 環境の問題
- 個人の心理的な問題
言語表出の基本と発達の個人差
意味のある言葉〜少しずつ単語が出てくるまでに大切な3つのことがあります。
意欲×言語理解×口周りの筋力
意欲は、コミュニケーションの基本で、やり取りしたい!と思ってもらうことです。
言語理解は50〜100くらいで表出に繋がります。
言語表出の前に言語理解が育ちますよ。
口周りの筋力は、0歳の口周りを想像すると、喃語は言えるけど、言葉は言いにくいって分かるかもしれないですね。
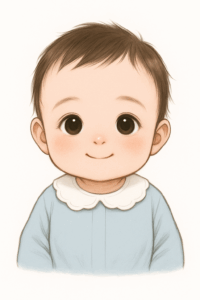
あぅあ〜〜
発達の個人差により、この3つが揃う時期は人によってバラバラです。
理解はどうかな?口周りの筋力はどうかな?意欲はどうかな?などと観察してみましょう。
聴力の問題
現在生まれたあと新生児スクリーニング検査という、聴力検査をしますね。
ここでpassとでても、実は聴力に問題があったということもあるのです。
おうちでとても簡単にチェックしてみる方法を紹介しますね。
聴力チェック
子どもの後ろに気づかれないように座り、おもちゃや手を叩くなどをして音を発する。
その時に子どもが振り向くかどうかを見る。
注意点
- 音の大きさを細かく設定することは出来ない
- あくまでも‘なんとなく’そうかもとわかる程度である
- 難聴確定とはならない
- 子どもが親の存在に気づいている場合がある
大きい音だと聞こえているけど、小さい音は聞こえていない場合もあるし、反応する(首を振り向かせたり体を後ろに向ける)筋力がない場合は聞こえていても見逃している場合があります。
心配事がある場合は必ず病院へ行きましょう
口周りの筋力不足
口周りの筋力が低下していると、発音がはっきりしなかったり、色々な形にならなかったりします。

0歳の子を想像するとわかりやすいと思います。
口周りの筋力を上げるには、離乳食も重要ですし、遊びの中で取り入れることもできますよ。
ストロー吹き
お風呂用のパズルを立てかけてストローで吹き、倒しながら遊びます。

好きなキャラクターがいる場合ダンボールで作ってもいいですよ!
長方形に切って半分に折ります。
上半分に好きなキャラクターを描いたら完成です✨
ダンボールだとこのような感じです。
(後ほどダンボールの写真を追加します)
コップで水をぶくぶく
コップに水を入れて、ストローでぶくぶくすることも、口の中や口周りの筋力がアップします。
ラッパや風船を吹く
風船は実際に膨らまなくてもいいんです。
力強く吹くことに意味があります。
ラッパは音も出るので楽しみながら口周りを動かすことができます!
口周りを動かす!あいうべ体操
こちらはあいうべ体操です。
家で気軽に出来ると思うので行ってみてくださいね。

歌を歌ったり、動物真似っ子遊びをしたり、とにかくたくさんお口やお顔を動かすことがポイントです!
絵本をみながら真似っ子遊び
こちらは言語聴覚士が作った絵本です。
オノマトペがたくさん書いてあり、イラストも見やすいです。
絵本を見ながら声をだす練習をしてみてくださいね。

オノマトペは、リズムや感覚とつながりやすく、子どもが言葉をまねして表現するきっかけになりますよ!
言葉の遅れとおうちの環境の関係
「言葉を話してみよう」「言葉って便利」って思ってもらえるような環境作りも大切です。
チェック!
- 大人があまり話しかけない
- 子どもの気持ちを汲み取って、言葉にする前に先にやってあげちゃう
- 一方通行の刺激(映像や音)に触れる時間が多くて、人とのやり取りが少なくなっている
こういうことが重なると言葉で伝える機会が減ってしまいます。

聞いてもらえた!という経験の積み重ねで、言葉の表出に繋がりますよ。
子どもに話しかけるときは、たくさん説明するよりもやりとりを楽しむことが大切です。
やりとりの方法としてインリアルアプローチがおすすめです。
この本もおすすめですよ。
個人の心理的な問題
言葉は、心の安心感と繋がっています。
緊張が強かったり不安を感じている時には言葉が出にくくなることがあります。
また、慎重な子は「間違えたくない」という気持ちから、声に出すのをためらうこともあります。

おうちの方も無理に頑張らなくて大丈夫ですよ。
ちょっと気になると思った時には、子育てや言葉のことを相談できる支援の場に繋がることも大切です。
親も子どももホッとできる居場所があることが、言葉の育ちを優しく支えてくれます。
言語表出についてのまとめ
言葉の育ちは体や心、環境など色んな要素が関わっていて、発達のスピードにも個人差があります。
「伝えたい」「わかってもらえた」という経験の積み重ねることが言葉の力を育てていきます。
ちょっと気になるというときは、相談できる場に繋がることも大切ですよ。

