こんにちは。ルチです。
今回は言葉がなかなか出ない子どもに対して、家庭でできる声かけの工夫をご紹介します。

うちの子なかなか言葉がでてこないし、どう声かけしたらいいかも分からない。
こんな風に感じることはありませんか?
実は、子どもの言葉の発達には、日常の声かけの仕方 も大きく関わっていますよ。
ちょっとした工夫で、子どもがもっと話したいと思えるきっかけをつくることができます
子どもの言葉が育ちにくいのはなぜ?
子どもの言語発達には個人差があります。
「同じ年齢のあの子はたくさん話すのに……」と感じて不安になる親御さんも少なくありません。
言葉が出にくい理由は決して1つではありませんよ。
こちらの記事に言葉が出にくい時に考えられる原因をいくつかあげています。
見てみてくださいね。
「言葉が遅れている=問題がある」というわけではなく、子どもにとって安心できる環境と言葉を育てたくなる声かけがあれば少しずつ言葉は豊かになっていきますよ。

そのための具体的な方法としてインリアルアプローチをご紹介しますね。
インリアルアプローチとは?
インリアルアプローチは、アメリカで生まれた ことばのやりとりを自然な環境の中で育てる方法です。
従来の考え方
従来の考え方では、まず言葉(単語)などを覚えてその後にコミュニケーション(やり取り)が出来るようになると考えられていました。
例えば
- 子どもが「りんご」という単語を覚える
- そのあとに「りんごちょうだい」など、少しずつ文章を話せるようになる
- それから会話のやりとりが広がっていく
このように、単語を覚えてからコミュニケーションを広げていくイメージです。
インリアルアプローチの考え方
インリアルアプローチの考え方では、コミュニケーションの中で、言語を習得していきます。

そのコミュニケーショをとる中でアプローチとして基本的な姿勢があり、言語心理学的な技法がありますよ。
ちょっとしたコツですね。
インリアルアプローチの言語心理学的技法
コミュニケーショをとる中で大人ができる言語心理学的な技法(コツ)が7つありますよ。
1つずつご紹介していきますね。
ミラリング
子どもの行動をそのまま真似をすることです。
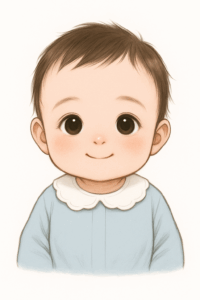
パチパチ(拍手をする)
パチパチ(拍手をする)

このように、動作の真似っ子をするんです。
子どもは大人が自分と同じ動きをしていることに気が付き、自分のやっていることを見てもらえてると感じることができます。
そうすると、安心して笑顔になったりもっと関わろうとしたりするんです。

繋がれたという嬉しさが生まれるんですね。
こうしたやり取りを繰り返すことで子どもはやり取りって楽しいという気持ちを育てていきます。
大事なのは同じことをしてるよということを子どもに伝えるように目の前でしたり、大きく動いたりすることです。
モニタリング
子どもの声をそのまま真似をすることです。
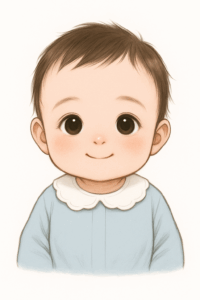
あばばば
あばばば

声や言葉をそのまま真似をして返すことです。
子どもは自分が声を出すと大人が反応してくれると気付きます。
そうすると、「声を出すと相手とやり取りができるんだ」「伝えられるんだ」という体験に繋がりますよ。

声を出すことって楽しい!と感じるきっかけになり、言語表出を促すことが出来るのです。
言語表出にはやり取りをしたいと思う意欲がとても大切なんですね。
単語で話す時のモニタリング
「ブーブー」と言ったら「ブーブー」と言う。
2語文で話す時のモニタリング
「パンちょうだい」と言ったら「パンちょうだいって言ってくれたね。パン食べようね。」
パラレルトーク
子どもの気持ちや行動を言葉にすることです。
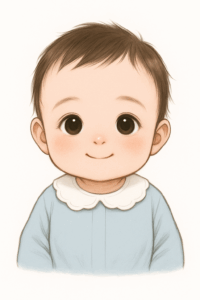
(車のおもちゃを走らせている)
くるまブーブー!くるまが走ってるね!

これは実況中継のように子どものしていることをそのまま言葉にしてあげるイメージです。
子どもにとって「ママやパパが自分のことをわかってくれてる」「見てもらえてる」という安心感に繋がります。

こういう時にこういう言葉を使うといえように、自然に学ぶことができますよ。
パラレルトークは自分の気持ちや行動を言葉で表せるようになる土台づくりに繋がる関わり方です。
お着替えの時のパラレルトーク
「さぁ!○○くんお着替えするよ。まずは服を脱いで、この車の服を着ようか。おててさん出るかな?ばぁ〜お顔もでるかな?ばぁ〜」
転けて泣いている時
「転けちゃってびっくりしたね。痛い痛いね。びっくりしたね。」
セルフトーク
大人の気持ちや行動を言葉にすることです。

今からお茶を入れるね。熱いから気をつけて持とう。そーっと。ゆっくり。

眠たくなってきたなぁ。ふぁ〜あくびがでちゃった。
大人が今していることや感じることをそのまま言葉にして伝えます。
子どもにとっては大人がどういう時にどういう言葉を使うのかを学ぶチャンスになりますよ。

語彙の理解を広げるチャンスにもなります!
大人が気持ちを表現してくれていると、安心感にも繋がります。
他の例もあげてみます。
買い物シーンでのセルフトーク
「あ、このお魚安い!美味しそう。今日の晩御飯お魚にしようかな。」
お片付けシーンでのセルフトーク
「よーし、まずはこのブロックをこの箱に入れるよ。よいしょ、そして、この車のおもちゃはここに置いて……」
体調が悪いシーンでのセルフトーク
「今日は頭が痛いなぁ。雨が降ってるからかな?ちょっとだけ横になろう。ゴロン〜。」
リフレクティング
子どもの言い誤りを、自然に正しい言葉を聞かせることです。
例えば子どもが猫を見て……

ワンワン!
にゃ〜ねこいるね。

このように自然に正しい言葉を返してあげます。
「違うよ。犬じゃない。猫だよ。」
このように子どもの表出を否定する声かけは控えましょう。

自然と正しい音をフィードバックすることが大切ですよ。
発音が気になる時
「さかな」を「たかな」「ちゃかな」と言った時に「違う。さ、か、なでしょ。もう1回言ってごらん」と言い聞かせるのではなく、「さかなだね。」と自然にフィードバックすることが大切です。
エキスパッション
子どもが話した言葉に、大人がことばを足してより豊かな表現にして返す方法 のこと。
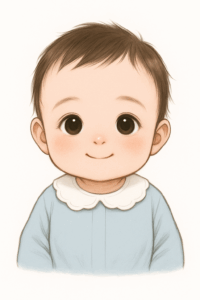
ブーブー!
ブーブー走ってるね。

このように、子どもが単語で話してくれた時は、2語文で返すように、子どもの言葉に少し言葉を足して返します。
2語文は「わんわんいる」のように2つの単語が繋がって文のようになっていることです。

ワンワンいた!
ワンワンいたね。お散歩してるね。

子どもの言葉を受け止めながら、自然に文を長くする力を育てられます。
モデリング
子どもがまだ言えないことばや表現を、大人がお手本として自然に示す関わり方のことです。
リンゴを指さしてる子どもに対して「りんごだね」と言ったり、「バイバイ」と言ったら「また明日ね」と言ったりします。
こうすることで、子どもは大人がどのように言葉を使うのかを自然に学んでいきます。

子どもが自分ではまだ使えない表現を耳から入れてもらう大切なチャンスです!
やり取りの力を更に伸ばしていくことに繋がりますよ。
ポイントは教え込むのではなく自然に見せてあげることです。
インリアルアプローチ×遊び
日常の中でいつでもインリアルアプローチはできるのですが、遊びの中で具体的な会話として例示しますね。
家庭菜園の中で
家庭菜園は、様々な色や形、重さや大きさを感じることができます。
トマトを見て「まだみどりだね」「赤いトマトだね。真っ赤だね〜!」と言うと、色を学ぶことができますね。
サツマイモやジャガイモの場合は「これ、とても重たいよ。大きいね」「これは小さいね」などと、重さや大きさを学ぶことができます。

「大きい・小さい」や、「重い・軽い」などの形容詞は、机上の勉強より日常の中で学んでいく方が概念を獲得しやすいですよ。
感覚遊び
感覚遊びは、声かけの宝庫です!
お米の感覚遊びでは「いっぱい」「少ない!」など、量の感覚を学ぶことができます。
こちらのリアルな動きをするお魚おもちゃだと「お魚さんいるね」「動いてるね!こっちきたよ!」「青いお魚、石の上にいる」など、様々な声掛けをすることができます。
声かけは教えるよりも寄り添う
今回ご紹介したインリアルアプローチは生活の中で自然と取り入れることができます。
大切なのは、正しく言わせることではなく、気持ちをわかってもらえた!という体験です。
ただし……
大人が「完璧にやらなきゃ」と思う必要はありません。
毎日の生活の中で、できるときにできる範囲で取り入れるだけで十分です。

親も子どもも、無理をせずことばを通じて一緒に楽しむ時間を積み重ねていくことが大事です。




